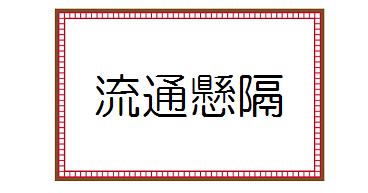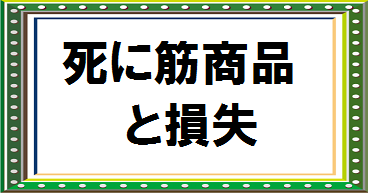経済循環とは?流通の役割をわかりやすく解説
私たちの経済活動は、「生産」と「消費」によって成り立っています。これらをつなぐのが「流通」です。
つまり、生産された商品が流通を通じて消費者に届けられ、消費されることで、再び生産が促される。このような一連の流れが「経済循環」です。
この循環をスムーズにするための媒介が「貨幣」であり、私たちはお金を使って商品やサービスを購入し、消費しています。
消費財とは?
消費者が購入して直接使う商品を「消費財」といいます。食料品や衣料品など、日常生活で使われるものがこれにあたります。
消費者は貨幣を支払い、消費財を手に入れ、使用することで「消費」が発生します。
生産財とは?
企業(生産者やメーカー)が商品を生産するために使用するものが「生産財」です。たとえば、製造機械や原材料などがこれにあたります。
生産者は生産財を使って商品を作り、それを販売して貨幣を得ることで経済活動が進みます。
流通懸隔とは?
「流通懸隔(りゅうつうけんかく)」とは、生産者と消費者の間にあるさまざまなギャップ(隔たり)のことです。主に次の5つの懸隔が存在します。
流通がなければ、これらのギャップを解消できず、経済循環は成り立ちません。
流通懸隔は次の2つに分類されます:
- 要素的懸隔:物理的なギャップ
- システム的懸隔:情報や価値に関するギャップ
要素的懸隔(3つ)
- 所有懸隔:商品は最初、生産者が所有しています。消費者が商品を使えるようにするには、貨幣を介して所有権を移す必要があります。
- 空間懸隔:生産された場所と消費される場所が異なるため、流通がその距離を埋めます。
- 時間懸隔:生産された時期と消費される時期が異なることがあり、在庫や保管などによって時間のギャップを調整します。
システム的懸隔(2つ)
- 情報懸隔:生産者は何が売れるのか、消費者は何が売られているのかがわかりません。流通によって売り手と買い手の情報が共有されます。
- 価値懸隔:生産者の売りたい価格と消費者の買いたい価格にズレがある場合、それを調整し一致させる必要があります。
流通業の重要な役割
流通業には、次のような役割があります:
1. 社会的役割(架橋機能)
生産者と消費者をつなぐ架け橋となる機能です。商品やサービスを必要な人に届ける役割を担っています。
2. 経済的役割
流通業が介在することで、経済全体がより効率的になります。具体的には次のような4つの原理があります:
- 取引総数単純化の原理
生産者と消費者が直接取引するより、流通業が間に入ることで取引の総数を減らし、効率化します。 - 集中貯蔵の原理
卸売業が一括して在庫を保有することで、複数の小売業が個別に在庫を持つより効率的です。 - 情報縮約・整合の原理
複雑な情報を簡潔に整理し、必要な情報だけを取引相手に伝えることで効率化されます。 - 規模の経済の原理
取引や配送を大量にまとめることで、単位あたりのコストを削減できます。
これらの役割によって、流通業は現代経済にとって欠かせない存在となっています。