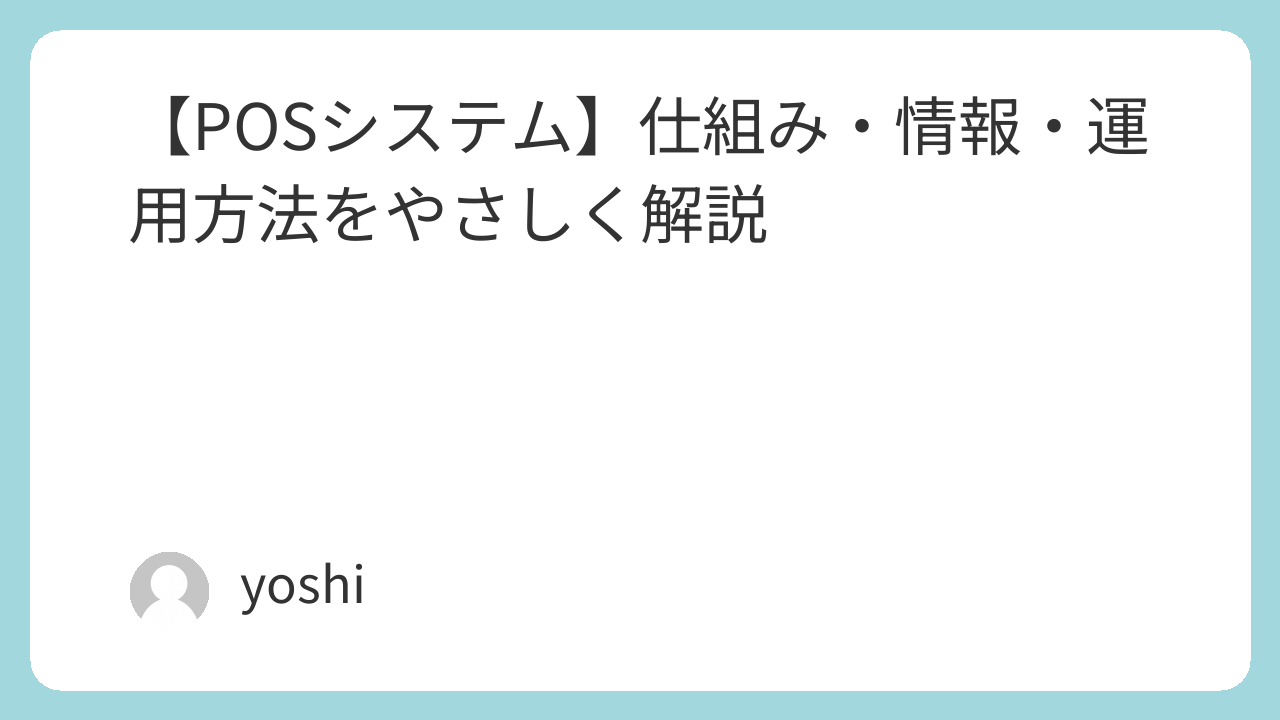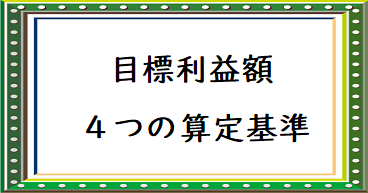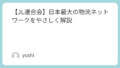POSシステムとは?販売管理に役立つ仕組みと運用ポイントを徹底解説
POS(Point of Sale)システムとは、「販売時点情報管理システム」のことです。商品の販売時点で自動的にデータを収集し、売れ筋の把握や在庫管理、顧客分析などに活用できる、販売管理の中核となる仕組みです。
POSシステムの定義と特徴
小売業向けの販売士ハンドブックでは、POSシステムを次のように定義しています:
POSシステムとは、小売業の経営改善活動に必要な購買情報を、発生時点で自動収集し、商品カテゴリごとに単品の販売動向を分析し、品ぞろえや販売管理に活用するコンピュータ&ネットワークシステムである。
このシステムには、以下のような3つの特徴があります。
- データの発生時点での自動読み取りと自動収集
- 収集した情報の加工と出力
- 利用者の職階や業務目的に合わせた情報活用
POSシステムで得られる5つの情報
- 商品情報:単品ごとの売価・数量など販売、仕入、在庫に関する情報
- 顧客・客層情報:誰が・どこで・どれだけ買ったかを示す情報
- 販促情報:特売やイベントなど販売促進活動とその影響(コザルデータ)
- 従業員情報:誰が販売したかなど、作業項目別・個人別の稼働状況
- 販売情報:決済手段や売場、関連購買に関する情報
最寄品におけるPLU型POSシステムの基本
食品や日用品などの「最寄品」では、JANコードを使ったPLU(Price Look Up)型POSシステムが基本です。JANコードには価格が含まれていないため、POSレジがJANコードを読み取ると、ストアコントローラが商品マスターから売価などを検索し、レジに返す仕組みとなっています。
JANコードと自社コードの使い分け
JANコードは一般的な商品に使われますが、分類情報を含んでいないため、小売業では独自に「自社コード」を設計し、商品分類や在庫管理に活用しています。自社コードの設計では、以下のポイントが重要です。
- 将来の品ぞろえ拡大に対応する網羅性
- 桁数はシンプルで短く設計
- 商品分類コードと商品コードを分けて管理
商品マスターファイルとその運用
POSシステムで正確な管理を行うためには、商品マスターファイルの作成とメンテナンスが不可欠です。
商品マスターファイルとは?
単品ごとに商品コード、商品分類コード、仕入先、仕入価格、標準売価、取扱店舗などを記録したデータベースです。POSシステムの中核を成す要素であり、その設計と維持管理がPOS運用の成否を決める重要なポイントとなります。
メンテナンスの主な内容
- 新規商品の登録
- 特売価格の設定と終了後の売価の戻し
- 廃番商品の削除
インストアマーキングとソースマーキング
商品にバーコードを付与する方法として、次の2つがあります。
- ソースマーキング:製造元・発売元が商品にバーコードを印刷または貼付(主に最寄品)
- インストアマーキング:小売店が独自コードを印刷・貼付(生鮮食品や惣菜など)
Non-PLU型POSシステムとは?
衣料品などの「買回品」では、価格を含んだバーコードを値札に表示するNon-PLU型POSシステムが用いられます。小売業が独自に商品コードと売価を設定・表示するのが特徴です。
顧客情報管理型POSシステム
販売時点で顧客情報と商品情報を同時に収集するPOSシステムもあります。運用には以下の2点が重要です。
- 顧客情報収集レベルの決定:客層データ(例:若者、中高年など)か、会員データか
- カード機能の決定:ID機能だけにするか、ポイント・クレジット機能を持たせるか
クレジット型POSシステム
クレジットカードによって顧客情報を収集し、売上処理・集計までを自動化するシステムです。主な処理の流れは以下の通りです。
- カードの自動読取
- 事故カードのチェック
- 売上伝票の発行
- クレジットオーソリゼーション(承認)
- 自動集計
POSシステム導入のメリット
ハードメリット(数字に表れる効果)
- 売れ筋商品の把握
- 在庫の適正化
- 人員配置の効率化
ソフトメリット(戦略的効果)
- 顧客ニーズの把握
- 販促活動の最適化
- 次回仕入れや商品展開のヒント
まとめ:販売管理の要、POSシステムを正しく理解しよう
POSシステムは、単なるレジ機能にとどまらず、小売業の経営改善や戦略的販売管理に欠かせないツールです。仕組みや情報の種類、商品マスターファイルの役割、ソースマーキングとの違いなどを理解し、効率的な店舗運営に役立てましょう。