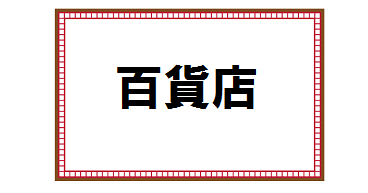 百貨店の運営特性
百貨店の運営特性 百貨店の運営特性
百貨店とデパートは同じ意味である。関東ではデパート、関西では百貨店と言う人が多いらしい。ここでは百貨店を使用する。西武百貨店=西武デパート東武百貨店=東武デパート百貨店(department store)買回り品を主体に最寄品、専門品まで幅...
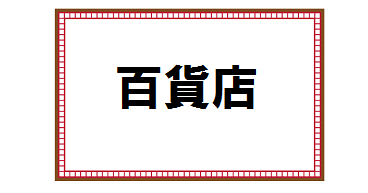 百貨店の運営特性
百貨店の運営特性 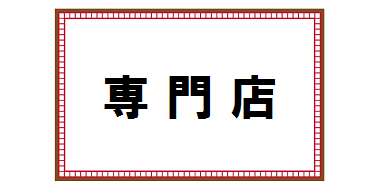 専門店の運営特性
専門店の運営特性  (RC)の運営特性
(RC)の運営特性  (RC)の運営特性
(RC)の運営特性  (COOP)の運営特性
(COOP)の運営特性  (COOP)の運営特性
(COOP)の運営特性  (FC)の運営特性
(FC)の運営特性  (FC)の運営特性
(FC)の運営特性  (VC)の運営特性
(VC)の運営特性 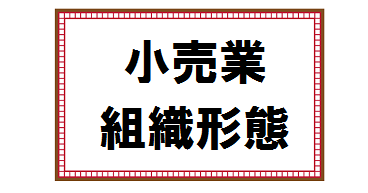 小売業の運営特性総論
小売業の運営特性総論 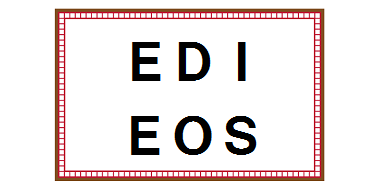 サプライチェーンの効率化とパートナーシップ
サプライチェーンの効率化とパートナーシップ  サプライチェーンの効率化とパートナーシップ
サプライチェーンの効率化とパートナーシップ 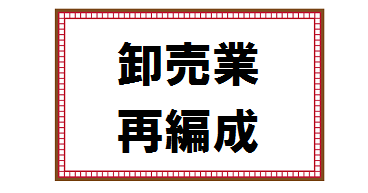 卸売業の構造と機能変化
卸売業の構造と機能変化 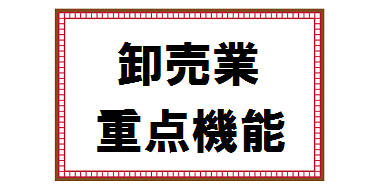 卸売業の構造と機能変化
卸売業の構造と機能変化 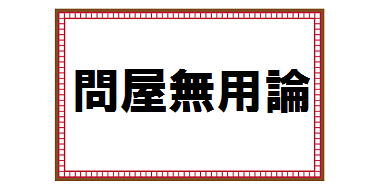 卸売業の構造と機能変化
卸売業の構造と機能変化 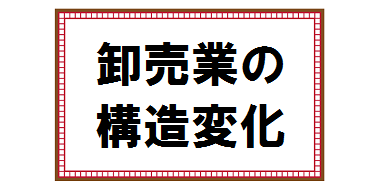 卸売業の構造と機能変化
卸売業の構造と機能変化 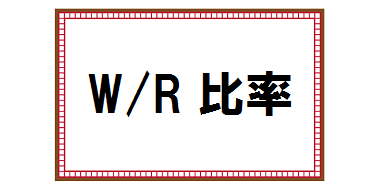 卸売業の構造と機能変化
卸売業の構造と機能変化 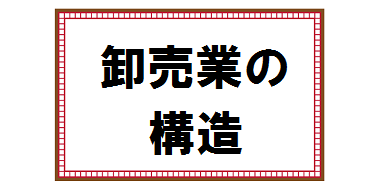 卸売業の構造と機能変化
卸売業の構造と機能変化